今からおよそ1400年前の推古2年(西暦594年)。
推古天皇の摂政であった聖徳太子が「霊地は近江国にある」と占い、駒の蹄に任せて永久に鎮護国家、仏法興隆を祈る道場を求めていました。そして繖山(きぬがさやま)の麓辺りに来ると、駒は歩みを止めて進まなくなり、傍らの松の樹につないで山に登ったところ、瑞雲(※1)がたなびく風光明媚な風景が広がっていたのです。聖徳太子は「積年の望みをこの地に得たり」と深く感動して再び山を下ると、松の樹につないだ駒が傍の池に沈んで石と化していました。この奇瑞に大いに霊気を感じ、直ちに山を『御都繖山(ぎょとさんざん)』と名付け寺を建立し、馬が石となった寺、つまり『石馬寺(いしばじ)』と号されたのです。その際に記された聖徳太子直筆『石馬寺』三文字の扁額(※2)、及び太子が駒をつないだ松の樹は本堂に安置しております。また、石と化した『石馬』も寺に至る石段下の蓮池に現存しております。霊験として語り継がれる、石馬寺が持つ霊力・霊気をあなたの心や肌で感じて下さい。
※1「瑞雲」めでたい兆しとして出現する、紫色や五色の珍しい雲
※2「聖徳太子直筆『石馬寺』三文字の扁額」聖徳太子直筆と伝わる額の文字を、石碑やパンフレット等のロゴに使用しております。


石馬寺は聖徳太子の建立以後、法相宗、天台宗と転宗し、近江源氏である佐々木氏の篤く帰依するところになりました。しかし永禄11年(1568年)、織田信長の上洛に抵抗した佐々木承禎との戦いによる戦禍を受け、伽藍や院坊のことごとくが信長による兵火に遭い、昔日の壮観を二度と見ることが出来なくなりました。さらに、豊臣氏が天下を取ると寺領及び山林を没収され、山主や僧徒は退散を命じられたのです。
慶長8年(1603年)、徳川氏により『石馬寺』が復興。寛永11年(1634年)3代将軍家光公上洛にあたり、旧神埼郡能登川町(現東近江市)に造営された御茶屋御殿(伊庭御殿)を移築して大方丈としました(旧本堂)。そして、正保元年(1644年)11月、宮城県松島にある瑞巌寺の雲居国師を中興祖として招き、臨済宗妙心寺派の寺院として現在に至ります。
石馬寺には、
国の重要文化財に指定されている
仏像11体をはじめ、
市の指定を受けた仏像や掛軸など、
数多くの貴重な仏教美術が
大切に守り伝えられています。
掛軸は通常非公開となっておりますが、
重要文化財に指定された仏像は、
拝観時にご覧いただけます。


阿弥陀如来座像
平安時代
十一面観世音菩薩立像
平安時代


役行者大菩薩腰掛像
鎌倉時代
その他の重要文化財
- 大威徳明王牛上像(平安時代)
- 持国天立像(平安時代) 二体
- 増長天立像(平安時代)
- 多聞天立像(平安時代)
- 役行者大菩薩脇立ち前鬼・後鬼像(鎌倉時代)


聖徳太子馬上像 二十二歳
伝/聖徳太子作

聖徳太子合掌像 三歳
伝/聖徳太子作
その他の重要寺宝
- 『石馬寺』扁額(聖徳太子筆)
- 太子駒繋ぎの松
- 十一面千手観世音菩薩立像(本尊:市指定文化財、鎌倉時代)
- 毘沙門天立像(市指定文化財、鎌倉時代)
- 地蔵菩薩立像(市指定文化財、平安時代)
- 閻魔大王坐像(鎌倉時代)
- 雲居国師坐像
- 釈迦如来坐像図(市指定文化財)
- 「不二門」扁額(中林梧竹筆)ほか
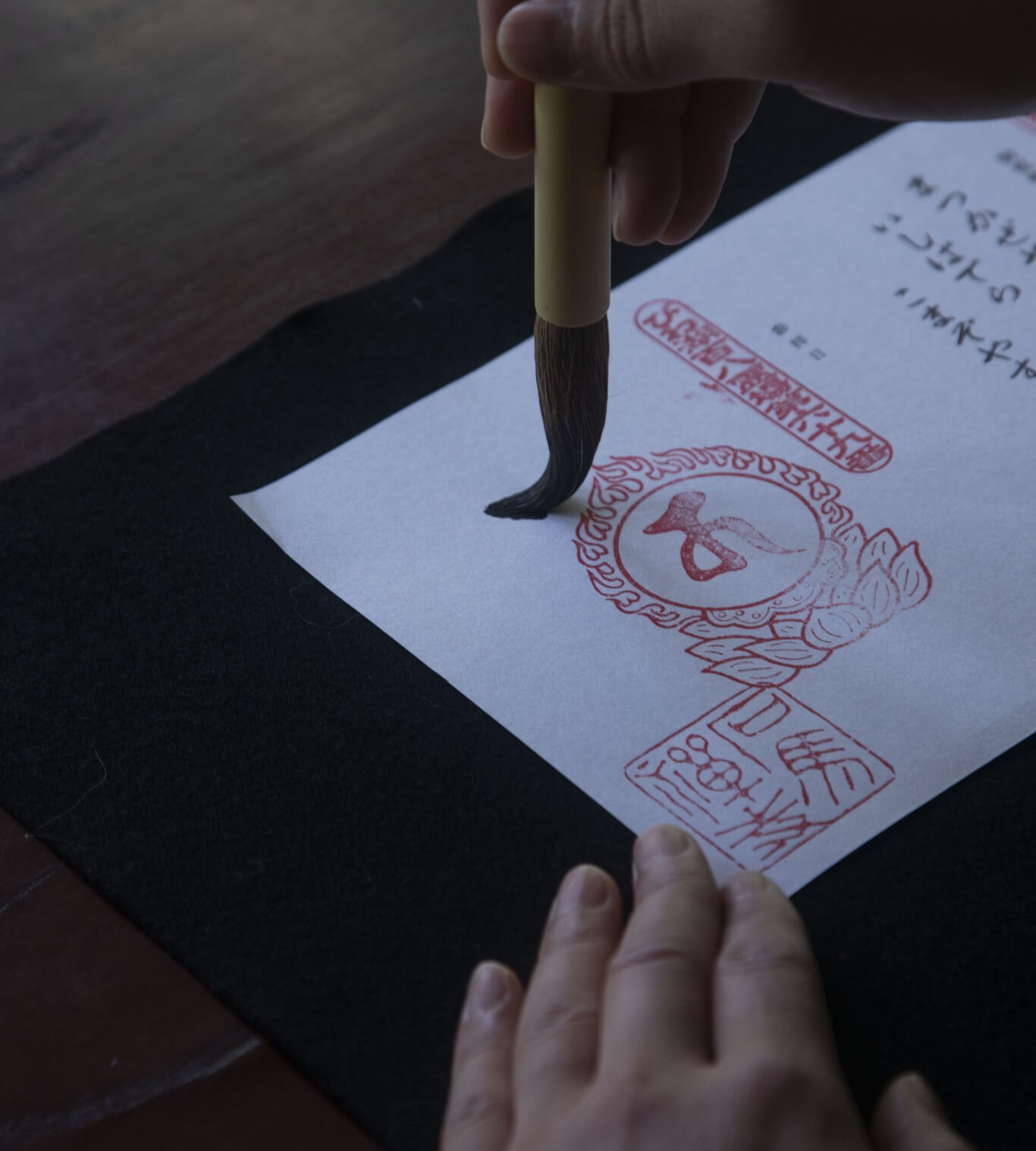
どなたでも拝観いただけます。
お気軽にお参りください。
静かな境内で行われる、
四季折々の行事をご紹介します。










